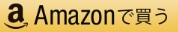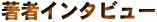
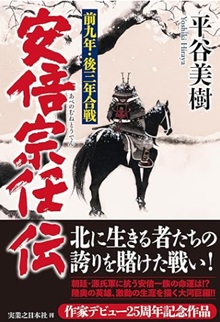
- 平谷美樹著
- 朝江丸装画/伊藤康子題字
- 実業之日本社
- 2530円、Kindle版2479円(税込)
- 2025.7.24発行
- 高橋政彦著
- エンジェルパサー
- 1870円(税込)
- 2021.9.13発行
稀代の〈謎学の語り部〉が、岩手の伝承や伝説の謎に挑んだ意欲作!
椎名誠氏、推薦!
謎に満ちた岩手の魅力が、読むにつれてさらに
ますます謎が深まる。
「30年ほど前から著者の高橋政彦くんと岩手のすみずみまでずいぶんと旅をした。
そのたびに大小さまざまな魅力的な謎に出会い、
その都度、政彦くんに解説してもらうという贅沢な旅だった。
本書は政彦くんの興味と知識の集大成だ。
この本を持ってまた彼と気ままな旅に出かけたい」
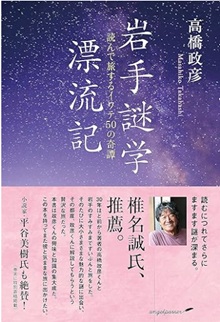
インタビュー中に出てきた関連本の情報はこちらにあります→「平谷美樹先生著者インタビュー関連本」

今号は、前号に引き続き新作を出された平谷美樹先生にお願いしました。
「作家デビュー25周年記念作品」と銘打たれた『安倍宗任伝 前九年・後三年合戦』は、平安時代の武将・安倍宗任(1032-1108)が主人公です。
7月に発刊後、すぐさま重版されたようで喜ばしい限りです。

一週間くらいで、わたしにとっては最短記録です(笑)
主人公が有名な武将ではないし、分厚いし(笑)、ちょっと驚いています。

そういう最短記録は、大歓迎ですね(笑)
発行元の「実日オンライン」(実業之日本社)を拝見いたしますと「刊行記念エッセイ」として平谷先生の「安倍宗任伝顛末」が掲載されてます。
ここを読ませていただいて、デビュー当時からずっと平谷先生にインタビューさせていただいてきているのに、歴史小説を書かれるようになったそもそもの経緯をうかがってなかったことに気がつきました(汗;)

まぁ、手短に語れる経緯はああいうことです(笑)

ということは、語られてない経緯が相当あると言うことですね(笑)
上記の「安倍宗任伝顛末」に、“わたしを歴史の世界に引っ張り込んだのは、二十五年来の友人である高橋政彦氏である。"と書かれている高橋政彦先生にもご参加いただけることになりました。
高橋先生初めまして、よろしくお願いいたします。

初めまして。よろしくお願いします。平谷さんを誘惑したのは私です(笑)

高橋先生の書かれた『岩手謎学漂流記 読んで旅するイワテ50の奇譚』を拝見すると、第1話が「蛇の島貞任伝説」でした。陸奥国の「前九年の役」が取り上げられていて、まさに『安倍宗任伝』の時代のお話しですよね。

私もいろいろ知っているというより、ちょっと不思議な話を知ると、そこをそのたび掘っていくタイプなので
正直、関心はあっても知らないことだらけ。安倍氏の時代のことはあまり詳しくないんです。
でも、その時代のことをロマンをまじえて後世に語り継いだ伝承は、探せばポツポツあるんですよ。
そもそも東北の古代史は敗北の歴史なので分かってないことが多く、それらはロマンという言葉に置き換えられがち。じつはこの方がいろいろ妄想して楽しめたりします。
で、25年ほど前、私と同じようなロマンで楽しんでくれそうな新人作家さんと知り合えたんです。
この方を誘惑して巻き込んじゃおうと。それが平谷さん(笑)。
そうすれば一緒に飲みながら語らえたりして楽しいし、うまくすると小説にしてくれるかも、なーんて思って、そういう話題を振れる仕事を打診してみたんです。

25年前というと、平谷先生がデビューした年ですね。まだ有望なSF作家としてとしか認知されてなかったと思いますが、どこから「ロマンで楽しんでくれそうな新人作家さん」という認識を持たれたのでしょうか。
あ、平谷先生については、小松左京賞でデビューされたので、なんとなくずっとSF作家なんだろうなとSFファンは思っていたという意味です(汗;)

平谷さんがデビューされたのとほぼ時を同じくして、私が立ち上げていた編集プロダクションで『ふうらい』というローカル季刊誌を創刊したんです。これはサブタイトルが「不思議羅針盤いわて」で、それこそ岩手の伝説や怪談や釣り紀行まで載った雑誌で、『岩手謎学漂流記』の原点みたいなものでした。
その編集部宛、読者の皆さんからいただいたメールの中に、なんと平谷さんもいらっしゃった。
ちょうど小松左京賞を受賞した岩手在住作家さんの新聞記事を読んだばかりでしたので、「もしかして同じ人ですか?」なんてお返事させていただいたら「そうです」と(笑)。
それ以降、怪談や釣りのネタで意気投合し、親しくさせていただくようになりまして。

そうだったんですね。最初の頃の平谷先生のインタビューを読み返してみたら、全くそっち方向の話題には触れてません。地元の岩手の話を振っていたら、また違うお話しをうかがえていたのになぁ(汗;)
『岩手謎学漂流記』の帯には椎名誠先生の推薦文があり、巻末に平谷先生の特別寄稿文が掲載されてますね。椎名先生もSF小説を書かれてますし、高橋先生はSFに興味はおありなのでしょうか?

正直、がっしり、どっとりとしたSFには、興味がないというより「読みこなせない」という感じです。お恥ずかしい話なんですが(苦笑)。短編作品や掌編(ショートショート)はナルホドとついていけるかなぁという感じです。科学の基礎知識がないもので。
椎名さんとは35年ほど親しくさせていただいており、きっかけは椎名さんの「あやしい探検隊」シリーズ。私が友人たちと作っているアウトドアグループが「あやしい探検隊」の友好組織にさせてもらってからのお付き合いです。もちろんそうなってからは椎名さんの本はジャンルを飛び越えてて全部読んで来たので椎名さんのSFも読んでいますが、SFだけが接点ではないんですよ。

ガンダムとかウルトラマンもSFだと思いますので、大丈夫でしょう(笑)
私は『本の雑誌』で椎名先生を知ったのですが、『アド・バード』は突然出てきた感じで驚喜しました。ヘンテコな生物たちのネーミングセンスの良さには、痺れましたねえ。当時回りでは結構はやりました(笑)
平谷先生も釣りとかカヌー(カヤック?)にお詳しいようなので、共通点が多いように思います。
『岩手謎学漂流記』を読んでいたら「南昌山塊が生む怪光現象とは何か」という章があり、ちょっと行ってみたくなりました。というのは、つい最近知り合いの岩手の作家の方が書かれた短編に「南昌山の思うところ」というのがあって、これはIBCラジオ放送で朗読もされたのですが、南昌山はUFOスポットでもあるとも聞きました。地元では有名なのでしょうね。

はい、地元では「南昌山塊=怪光目撃が多い」ということである程度知られいます。
この山は、その山容からして独特の怪しさもあったり、宮沢賢治が「銀河鉄道の夜」の発想を得たという逸話もあったりして、得も言われぬ雰囲気を持っています。
しかも、実際に、いわゆる異星人と関係のあるUFOかどうかは別にして、怪光の目撃は多く聞きます。もちろんその正体や原因はさまざま語られたり、いや、あれは本物のUFOだ、なんていう信者もいたりしますが、とにかく「面白がることができるスポット」ですので、私は結構興味を持って眺め続けています。

そういうスポットが近くにあるのはうらやましいです。
四章五章の忠衡や義経に関する考察も面白いですね。「義経北行伝説」とか金山とか、まさに平谷先生の小説の背景とダブって見えました。

いえいえ、私は伝説を拾って面白がることはできても、それをもとにして物語を創作するのが得意ではないので、義経北行伝説がいまだに伝承されていることとか、そこに忠衡のような興味深い人物がいることとかを平谷さんにお教えして、もしかしてこれって裏があるんじゃないですかね、とか、こんな秘密があるんじゃないですか、とか、酒の肴にして楽しむまでしかできません。そうした中から、平谷さんが興味を持ってくださって、ネタにしてくれたら嬉しいなぁ、なんて一人でワクワクほくそ笑んでいましたけどね(笑)。

まんまとその手に乗って、今ではドップリ浸かっております(笑)

読んでみると、ドップリなところが色々とありました(笑)
『柳は萌ゆる』の主人公楢山佐渡の介錯をしたという江釣子源吉一族の150年は、もう調査されて平谷先生にお伝えされたのでしょうか。

江釣子源吉さんについては、その存在を平谷さんの方から教えてもらいました。その後、ひじょうに興味を持ってお墓参りしたり、調べたりしているうち、私の故郷である宮古とも繋がりがあることを知り、今後こっちの方もドップリ浸かりそうです(笑)

続報をお待ちいたします(笑)
一生に一度だけ願いを叶えてくださるという「能傳房神社」。平谷先生は、願掛けをされたのでしょうか。

願掛けして、ほかの神社には浮気していないのですが、願いは叶ってはいませんね(苦笑)
けれど、願い以外の所で、まずまずの人生を歩んでいますから、まぁいいのかな。

なんの願掛けかはちょっと気になりますが、個人情報ですね(笑)
「盛岡城下と鬼門封じ」で論じられている盛岡城と盛岡八幡宮や一直線に並んだ神社群は結界を意図したものではないかという考察が面白いです。
平谷先生も、かつて雑誌『ラ・クラ』の「平泉夢想紀行」で、平泉という保(町)の設計が面白い(表向きには恭順しているように見えるが、腹の中では舌を出している)という(笑)
岩手(北東北)では、後々のことを色々と考えて造られた町が、多の地域より多いのでしょうか?

盛岡城下の鬼門封じについても、その平谷さんの考察に刺激を受けての視点です。盛岡城の鬼門の方角に、まさにオフサイドラインのように点在する神社を地図で見つけ、じつに歩いてみて、さらに小社まで発見した時、やはりあるんだぁと感激しました。
平谷さんがお詳しいと思いますが、方位にまつわる風習や信仰は北東北もよその土地と同じなのではないでしょうか。

方位に関する風習は、おそらく陰陽師が都から持って来たものです。多賀城にも、胆沢城にも都から来た陰陽師がいましたから。平泉も四神相応の思想で作られています。

我が町の安倍晴明のお墓がある神社に行って、四神相応の思想で道(階段)がつけられているのかどうか聞いてみます。
ところで、ひょっとして、高橋先生は『ラ・クラ』にも関係されていたのでしょうか。

はい、ラ・クラの初代の副編集長でした。
2006年創刊の「ラ・クラ」は途中で体制が変わり、現在の川口印刷工業が発行元になりました。その変化のあたりで私は退き、あとはノータッチです。
雑誌は創刊までの企画作業のカオスさが楽しいので軌道に乗ってからは自分の役目ではないかなと思っていたタイミングでした。

それが高橋先生のスタンスなんですね。
平谷先生の著作には、たたら衆や隠し金山がよく出てきます。『岩手謎学漂流記』にも「兜明神岳貞任黄金埋蔵伝説」の章がありました。ここなどは、椎名誠先生が探検に行かれそうな(笑)

35年来のお付き合いをさせていただいてきた椎名さんは、北への旅に郷愁を感じてくださっているようで、嬉しいことに、特にも岩手には愛着を感じてくださり、よく来てくださいます。
私個人はどうしても岩手限定、少し足を伸ばしても東北までがテリトリーなのに対して、椎名さんは若い頃から世界の、それも辺境地を中心に旅され、じかに見聞されて来た方なので、さまざまな国の習わしや信仰、それに伝承に造詣が深い。ですから、おそらくあと20歳若かったら(※現在81歳)私の誘惑に乗って(笑)兜明神岳に埋蔵金探検に乗り込んだかもしれませんね(笑)

え、椎名先生ってもうそんなお歳になられたんですか。←人様のことは言えないけれど(汗;)
個人的には、「古代文字探検へのいざない」で取り上げられていた北海道異体文字に似ている古代文字に一番ロマンを感じました。その後新たな知見は得られたのでしょうか。

残念ながら新たな探検には出かけられておりません。熊が怖くて(苦笑)
それにしても「古代文字」は本当にロマンに満ちたテーマだと思います。その多くの出所が怪しい古史古伝というのも含めて面白さを感じます。もちろんすべてを盲信するようなことではなく、よく考えられているナァという裏方的関心です(笑)

熊を正しく怖がるのも大事なことなのですね。
今回の『安倍宗任伝』では、敵役の木幡橿几に痺れました。卑劣きわまりなくて嫌なヤツですが、極めて有能。ドラマ化されたら木幡橿几を演じた役者さんの当たり役になりそうです。だいたい、平谷先生の描く敵役は存在感があって魅力的ではあります。
木幡橿几にはモデルとかがあるのでしょうか。

モデルはありません。
同じような役が「義経になった男」にも出て来ます。
2人とも「己と異質な者を嫌悪する象徴」として描いています。
人間は誰しも持っていますよね、その感情。完全な朝廷側でもなく、武士側でもない。そういう敵を作っておきたかったんです。

『義経になった男』だと悪僧の“禅林房覚日”かなぁ。
そういえば、恒例のエフエム岩手の月曜ブックシェルフを聞かせてもらいました。
第六章の「厨川(くりやがわ)」の凄絶なシーンを選ばれたので驚きました。岩手の女子衆、積年の恨みもあるとは思いますが、怒らせると怖い……末代まで祟られそう(汗;)

今までの朗読では、阿部アナに気は強いけれど、あまり極端な感情を出さない場面をお願いしていたので、今回は「激情」を演じて欲しいと考えました。
リスナーさんからも「初めてああいう声を聞いた」と、絶賛されてました。

さすがプロですね。今までは《貸し物屋お庸》の「お庸ちゃん」のパートが多かったので、「激情」を現すシーンも無かったような。
放送で「二日後(8/20)に北上市で講演会がある」とうかがいましたが、その講演「作家平谷美樹の造り方」で、何か面白い質問は出ませんでしたか?

「小説を書いているのだけれど、最後まで書ききれないで途中でやめてしまう」というお話がありましたね。
「それでいいんです。書いているものよりも面白いものを考えついたら、そっちを書いていくというスタンスでOK。いずれ最後まで書いてみたいという作品に行き当たりますから。それまでは途中までの小説をどんどん書きましょう」
と答えました。私自身、アマチュアの頃、そういう時期がありましたし、今でも中断している作品はあります。

なかなか有意義な講演だったようで、近くの方がうらやましいです。

「講演」は、参加者さんたちに笑ってもらって、楽しく終われました。

地元というと、金ヶ崎町立図書館には、平谷先生の作品が展示してあるし、同図書館に行かなければ読めない作品もあったとのこと。これも面白い試みですね。

「図書館小説」の一編を映画にしようという動きがあったんですが、コロナで中断。今年、また動き出しています。

「町報」的なパンフレットに「町民による映画化が決定し撮影が始まった」と書いてありました。平谷美樹さんによる『図書館小説』は、もうクランクアップしたのでしょうか。

今、パイロット版を撮って、編集の最中のようです。そろそろ出来上がる頃かなと。

それは完成したらぜひ拝見したいものです。
これも全く知らなかったのですが、漫画誌「いわてマガジン」で《百夜・百鬼夜行帖シリーズ》が原作の漫画の掲載が2020年から始まっていたのですね。
同じ《夢幻∞シリーズ》の「冥界パティスリー 第1話 世界を壊すケーキ(1)」(大平しおり著,ゆうしようイラスト)は、岩手の作家さんによ伝奇モノ(?)で、《百夜・百鬼夜行帖シリーズ》や《貸し物屋お庸シリーズ》にも通ずる暖かさを感じました。

残念ながら「いわてマガジン」は終わっちゃいました。
大平さんは「もしよかったら」とお誘いしたのです。

岩手で、着々と独自の文化ができているようですね。

「百夜」はやっと新作を書きまして、編集者さんに送りました(笑)10月くらいにアップされると思います。

おお、《百夜・百鬼夜行帖シリーズ》新作お待ちしてます(笑)
月曜ブックシェルフで、岩手の本屋さんの売れ行きベスト5が紹介されていたのですが、岩手らしさが出ているんじゃないかと思いました。
『安倍宗任伝』が堂々の二位、「岩手のおかず」が五位で、一位が『ものいわぬ農民』(岩波新書、1958)。こんな昔の本がなんで?と思いググったら、俳優の水上恒司さんが、「あさイチ」で読んだと言われたみたいですね。ちょっと読んでみたら、なかなか興味深い内容でした。岩手出身の大学の同級生から、日本のチベットなんて言われることもあると聞いたこともありました。
平谷先生が常々口にされたり、著作の中に込められている思い、高橋先生が『岩手謎学漂流記』の「はじめに」で語られている“被害妄想”(岩手の民として服従しなければならない側としての苦い水を飲まされ続けてきた歴史)等々は、岩手の人たちのなかでは今でも共通認識としてあるのでしょうか。

意識しているか無意識にかは別にして、幼少の頃から何気に耳にしている郷土の歴史は、時代がいろいろながら、いつも決まって敗北の歴史ばかり。それを薄々感じつつ、後ろ向きな思考が根付いている気がします。負け続け、搾取され続けて今があるのですからどうしようもない。
でも、興味を持って掘り下げていくと、意外とすんなり負けただけでないことに気づきますし、より一層そうあって欲しいという想いにもなりますよね。
そういったこともよく平谷さんと酒の肴にするので、平谷さんが描く郷土の先人たちは負け犬ではなく、何かしらのメッセージを残してくれる。平谷さんの中にも「そんなもんじゃなかったはず」「そうあってもらいたい」という強い願望があるのではないでしょうかね?(笑)

東北に生まれたコンプレックスのようなものはありますね。
今は少なくなったけれど、「方言を笑いのネタにする」というのがありました。
随分昔、集団就職が盛んだった頃は、学校で方言を「悪い言葉」として教えた時代もあったようです。
岩手県人以外と話すときには共通語を使うようにしていますが、ラジオで自分の話しているのを聞くと、イントネーションに岩手弁が滲んでいるのが判ります。
本当は、堂々と方言を喋りたいのですが、わたしの言葉は南部の方言と伊達の方言が入り交じっているので、やっぱり恥ずかしかったりします(苦笑)
安倍氏、藤原氏の滅亡、阿弖流為(アテルイ)の投降――。いずれも根底には、「これ以上戦えば故郷が焦土と化す」という思いがあったと信じています。そこに至るまでの戦略はフィクションですけれど。

綿々と続いている「故郷(ふるさと)のために今を堪え忍ぶ」思想が共有されているんでしょうね。
古代東北の族長である阿弖流為(アテルイ)って、坂上田村麻呂に降伏したみたいだから、その当時から「この地を守らなければ」の思いがあったと……
また、ここらあたりの時代のお話しを読ませて下さいませ。

そうですね。次は藤原基衡を書こうと思っているので、資料を調べながら面白い切り口を思いついたら、遡って書くのもいいかもしれませんね

平谷先生、高橋先生、今回はお忙しい中インタビューに応えていただきありがとうございました。
高橋先生には、ぜひ『岩手謎学漂流記2』をお願いします。あ、全く別の「謎学」本でも良いのですが(汗;)

ありがとうございます。『岩手謎学漂流記』に収められたシリーズ・コラムは、地元タブロイド紙で今も連載が続いているので、続編を出せるぐらいはすでにまとまっているのですが、どうも出版となると厳しい時代のようで(苦笑)
ま、それにめげず、ライフワークと思って地道に書き溜めていきたいと思っています。

お二人の新たな連係プレーを期待してお待ちしています。
電子版のみの《百夜・百鬼夜行帖》シリーズは、《修法師百夜まじない帖》シリーズ3巻を含む110巻。
2015年「BARD」を設立。様々な領域のプランニングや取材、執筆、編集に関わる業務を展開している。