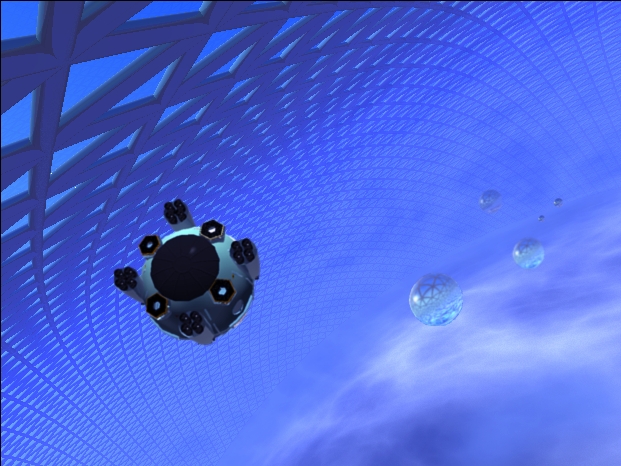|
「その正体はどの記録にも残されていない。理由はわからないけどなぜか意識的に抹消されたらしい……ともかくある克服不能の災厄に地球が見舞われたとき、やむなく人類は自分たちの故郷の星系に見切りをつけてふたつの計画に地球生命の存続を托すよりなかった。ひとつは『ギルガメッシュ』。もうひとつが『ワンダーランド』。前者は銀河のどこか別の場所に地球環境を再現するためのものであり、後者はそれが完了するまでの長い期間、人類の遺伝および知識情報を当時銀河ハローをかすめつつあった超巨大ブラックホール『うさぎの穴』のエルゴ圏に凍結保管することを目的としたものだった。まあ、それらがまがりなりにも成功したおかげでいまぼくら一家はここに存在しているわけだけどね……」
「古き良きインターフェイス『アリス』に!」カシルは手にした蓋つきコーヒーカップを捧げた。
「異議なし――ともかく『ギルガメッシュ』計画のためにティプラーが予言したフォンノイマン型テラフォーミングロボットが木星系から銀河にむけて放たれた。ぼくを含めた一般の人たちの知るところではそれらはすべて『イシュタル』と名づけられた一連の巨大なラムジェット船だった。ところが銀河系内を長時間飛行するにつれて宇宙線の影響かなにかでそのなかの一部のプログラムが変質した。他星系の資源を利用するかわりに手っ取り早く仲間を襲いその身体を解体して増殖するものが生まれてしまったんだ。それが『肉食』の狂ったイシュタル機械――『イルスター』だ」
「まあ、それが世の常識というやつなんだけど……でも人工知能の専門家はそれには疑問を抱いている。そもそもティプラー自身『フォンノイマン型機械』を提案した理由はテラフォーミングじゃなく太陽系外に高度な文明が存在しないことを証明するためだったの。そんな文明があったら他の文明にコンタクトすべく自己増殖する探査機を送りだしていないはずがない。にもかかわらずいまだそれらが地球に到達していないということは少なくとも銀河系近傍に人間以外知性を持った存在がいないという証拠だ、とね。当然その議論に対してすぐさま反論がでたわ。つまりまともな知能の持ち主であるなら自分たちにとって危険な存在となりかねないそんな自己増殖ロボットをそもそも宇宙空間に放ったりはしないだろう……」
「地球人類はまともでなかったというわけかい? でも彼らはそのとき切羽詰まっていたのだし――」
「それで危険を顧みず? そうかもしれない。でもティプラーへの反論以前にそもそもそうした自己増殖型の機械は果てしなく数が増えてしまって現実には到底使えそうもないとは思わない?」
「うん、確かに以前からぼくも疑問に感じてはいたんだ。ほうっておいたら『イシュタル機械』はありとあらゆる星系の資源を食い尽くしてしまうはずだ。最終的には銀河系そのものが『機械』で置き換えられてしまうんじゃないかなって」
「まあ実際にはそこまではいかないだろうけど、果てしなく増殖する機械が脅威であることは確かだわ。そんな単純な理屈をご先祖さまが気づかないわけがない。ということは彼らが造った『機械』はそういうものではなかったってことじゃない?」
「じゃあいったいぜんたいどういうものだったと思う?」
「ロボット工学ではこの種の問題の解決法はひとつしかないの。つまり『スマリヤンのロボットの島』のやり方よ」
「『スリムヤン』? 細身の中国系かい?」
「わざと間違えているでしょ。レイモンド・スマリヤンは二十世紀から二十一世紀にかけて活躍した数学者にして論理学者にして魔術師。白いお髭の素敵なおじいさまだわ」
「ふうん、意外だな。そういう趣味だったのね?」
「なに言ってるの。まじめに聞いてよね――とにかく彼が書いた『無限のパラドックス』という本のなかに架空の島が登場するの。もともとはロボットのプログラムの例を借りて自己言及、ひいてはゲーデル数と論理式による引用の話題へとつながっていくのだけど、それは今はおいておいて――その島ではたくさんのロボットたちがどったんばったん大騒ぎをしている。あるロボットはただ無目的に歩きまわり、べつのロボットは出会った相手をひたすら破壊する、さらにべつのやつはばらばらになった部品から新しいロボットを組み立てる、といった具合。もっとよく観察するとある種のロボットはもっぱら特定の種類のロボットのみを造り、あるいは壊すことになっていることがわかるの。XはYを造り、造られたYは今度はXを造る。あるいはXはYを造り、YはZを造る、だけど完成したZはつぎにはXを破壊する――さまざまなパターンがあるわけ。スマリヤンはけっきょくのところこうしたロボットたちのふるまいはプログラム相互の関係を規定するわずか八つの引用的言及にかかわる規則によって決定できることを示した――」
「ううむ、その話、大幅にはしょって結論だけというわけにいかない?」
「はしょると要点がよくわからなくなっちゃうんだけどな。つまりね、いままでイシュタル機械はただただ自分自身と同じXを作り出すだけのロボットと考えられてきた。でもそれでは集団として安定して存続できないのよ。むしろイシュタル機械もロボットの島のそれのように互いに複雑な関係をもつ複数のグループとして作り出されていただろうと考えるべきなの。いいかえるなら『イルスター』という存在は偶然生まれたものではなくて当初から『ギルガメッシュ計画』の必然的な要素だった、ということになるかな」
「ふーむ、なるほど――しかしそれがどう『長老機械』とつながる?」
「考えてみて――他のフォンノイマン機械を破壊するフォンノイマン機械という存在は本質的に自己矛盾を含むわ。もしそれらが『あらゆる機械』を破壊すべくプログラムされていたとしたら、最初に自己増殖したとたんに自分たち同士で壊しあいをはじめてしまうでしょう。それでは『イルスター』は長くは生き延びられない。いっぽうそれが自分と違った種類の機械だけを破壊するようにプログラムされていたら? こんどは『イルスター』自身がフォンノイマン機械として無限増殖をはじめてしまう。それではそもそも存在理由がない」
「なるほど、言われてみればたしかにそのとおりかも知れないね」
「それを解決するためにはスマリヤンの方法に従ってはじめから機械そのものに幾つものタイプを設定し相互の関係――壊したり産み出したり――を決めておけばいい。そしてたぶん現実にそうしたものとしてイシュタルたちは作り出されたのでしょう……。でもそうしたところで長期間にわたってはたしてその集団が安定するかどうかは保証のかぎりではないのよ。スマリヤンもそのあたりは実際にそうした実験をやってみないことにはわからないと言っている。それがたとえ決定論的なシステムでも複雑な相互作用を長い時間行うなら結果がどうなるかを予想することができないから。そして、もし地球人類がそこまで考えたなら、たぶん逆手をとって機械を製造する段階で非決定論的なプロセスを導入したのかも知れない。つまり自己再生プログラムにある種の冗長性とゆらぎを持たせるということ。たぶんそれは環境を認識してそれと相互作用しつつ自分と少し違ったプログラムを持った機械を作り出すようにデザインされていたはずだわ」
「――いわば人為的に導入された突然変異と自然淘汰、ってわけだね」
「うん、機械たちはそのときどきの相手によって獲物になったりハンターになったり、同盟を結んだり敵対したり、複雑な関係のなかでひたすら生存競争をつづけたはずよ。そうした集団に何百万年という時間を与えれば地球で生命に起こったのと良く似たことが起こったとしても不思議じゃない」
「……適応と進化か?」
「そう。さらに最終的にそのプロセスが生み出すものがチューリングマシンの限界を超えた推論が可能な実存段階(エグジステンス・レベル)の知能であってもいい……。つまり『長老機械』と呼ばれる神話的存在にまつわるシーカーの噂話もあながち法螺とも言えなくなるの。銀河のどこかに人間に匹敵するほど賢くなった機械たちの種族がいる――古の地球人たちはたんに自分達の惑星と良く似た環境が都合よく見つかることに賭けていたわけじゃないのかも知れない。それをゼロから作り出すことのできるほど強力な知性がいずれ誕生するように慎重に配慮していたのだとしたら?」
「進化の究極で人間に匹敵する意志と創造性をもつにいたったティプラー・フォンノイマン機械――人の知恵を持ちながら無限の時を生きることができるそれらはすでに神にも等しい存在になっている、というあれか。うーん、こいつはまさにオールマイティのカードだな。そんな『機械じかけの神々』が力をあわせれば、たしかにこんな途方もない世界も創造できるかもしれない……」
ウィリアムは観測窓から外を眺めながらつぶやいた。
*
『イレギュラー』に近づくにつれ風向きが不安定になってきた。あきらかに突出したその形状が大気の流れを乱しているようだ。周囲の空間に雲が増えしばしば観測窓を雨粒が濡らす。カシルは操船にかなり苦労している様子だ。星系内クルーザーの球状の船体は乱気流のなかでの飛行を想定してデザインされたわけではないのだから当然といえば当然だった。
すでに『サガ』は破断した『辺(エッジ)』から三キロほど距離をとったまま根元から先端部分にむかってゆっくりと移動しつつあった。カシルほど視力のよくないウィリアムにも『蜘蛛』たちの隊列が蠢くさまが肉眼で確認できる距離だ。隕石は『辺(エッジ)』が『頂点(ヴァーテックス)』に接する十キロほど手前の部分を直撃したらしい。近いほうの『辺(エッジ)』の付根は破断して折れまがり幾本かのケーブルのようなものでからくも支えられている。反対側の『頂点(ヴァーテックス)』の付根部分にも『辺(エッジ)』がえぐり取られた跡の巨大なクレーターが見える。しかしカシルが予想したような特殊な構造材の存在はすくなくともこの位置からでは確認できなかった。
「またまた予想を覆す結果だな。『辺(エッジ)』の構造全体が内部に埋め込まれた複数のケーブルで支えられているだけみたいね――たぶんカーボンナノチューブを織り上げたものでしょう」
「圧縮に強いダイヤモンド結晶格子は捻れには脆い。しかし引っぱり強度にすぐれたナノチューブなら耐えられる。なかなか理にかなった構造だな」
「理にかなっているかも知れないけど道理にはあっていないわよ。仮になにかの構造材が隠れているとしても、ああしてまがりなりにもケーブルでぶら下がっていられるということは『辺(エッジ)』全体は大した重量であるはずはない……」
カシルはモニター画像を見ながら不機嫌そうに言った。
「いったいぜんたいここの大気をつなぎとめている力はどこからわいてくるの? 腹がたつなー。納得いかないなっ?!」
いきりたつカシルに、ことここにいたってはウィリアムも申し開きのしようがなかった。――なんで『申し開き』しなきゃならないのかよくわからないが――とにかく『辺(エッジ)』が予想していたよりずっと軽いことは間違いなさそうだ。ということは……。
「『頂点(ヴァーテックス)』がとてつもなく重たい?」
「まさか。もしそうなら『頂点(ヴァーテックス)』の質量は十京トンのオーダーってこと――そんな小惑星なみの質量を結びつけておく力が通常物質である『辺(エッジ)』にあるはずない。ほんのわずかでも歪みが加わったら最後ジオデシック構造そのものがばらばらに砕け散ってしまうはずよ……」
「そうだよなあ。それじゃ重力はいったいどこからわいているんだ? やはりこれは『重力制御装置』しかないんじゃないか?」
「ううむ。でも、それってほとんど『神の奇跡』と言っているのと同じよね」
それからかなり長い時間黙り込んだあとでカシルは言った。
「重力を制御できるってことはたとえブラックホールの内部からでも戻ってこれるってことよ。そんな時間も空間も因果律さえも超越した存在は文字通り神にも等しいわ。いくらなんでも『長老機械』たちが全能の神そのものになったなんてわたし到底受け入れられない。これには必ずなにかちゃんとした説明があるはず……」
カシルはきゅうにコンソールに背をむけると操縦席へと漂い移った。
「何をするつもり?」
「あなたがいつも言ってるじゃない? 実証精神の武器は実験と観察以外になにもないって――ここで仮説をもてあそんでいても仕方ないもの。もっとあそこに近づいてじっくり眺めてみるのよ」
*
『サガ』の展望窓の外いっぱいに破壊された『辺(エッジ)』の先端部分の眺望がひろがっていた。まずは断崖絶壁にうがたれた巨大な洞窟という印象。しかし折れて砕けた破片はすべて『蜘蛛』たちが運び去ったうえでさらに材質表面を規則正しく削り取っていっているためちょっと方向を替えて眺めると上空から鳥瞰する広大な石切り場にも見えなくはない。洞窟そのものは果てしなく奥へ続く暗がりでしかなく、すでに『西』――というか世界の反対側へと傾いた赤暗く弱い陽光のもとでは内部を観察することはほとんど不可能だった。
「残念ながらめぼしい発見といったものはないわね。……そっちはどう?」
カシルが反対側の『頂点(ヴァーテックス)』に狙いをあわせた船外望遠カメラを難しい顔で操っているウィリアムに尋ねた。
「薄暗いうえにときおり雲が邪魔をしてあまりよく細部は見えないんだ。全般的な印象としてはこちらの付根部分はすっかり整地されて新しく『辺(エッジ)』を架ける準備万端終わっているといったところかな。一見えらく端正なクレーターだよ。内部には放射状や同心円状の線が見える。配電ケーブルなのか、通信ラインなのか、ひょっとしたらメンテナンス用の通路かも知れない。加えてきちんと等間隔に並んださらに小さなクレーターが六つある。これもなんのためのものかはわからないな。あるいはあれがきみの予想している超強度構造材の土台かも知れない。各々の小クレーターのすぐ外側、大クレーターの縁の部分六カ所に『蜘蛛』たちが群がっている。どうやらなにか大きな構造を造ろうとしているところらしい……」
「それってたぶんケーブルの敷設装置よ。こちらの破断面にもそれらしきものが見えるから――まずカーボンナノケーブルをわたして足場を造り、それから『辺(エッジ)』本体を造っていくのでしょう」
「なるほどむかし地球で吊り橋を造ったのと同じ工法か……」
「それにしても妙だなー。内部は完全にがらんどうみたい。これって結局のところ『頂点(ヴァーテックス)』の間に架け渡された巨大な中空のチューブにすぎないんだわ。けっして何かを支えるための構造物じゃない……」
「ねー、ぱあってやって? ぱあっ、て」
展望窓にひっついて熱心に外を眺めていたミヒョンが唐突に言った。
「なんだい、そのぱあっ、て?」
「照明弾のことよ。『辺(エッジ)』の中が暗いから照らし出してくれって言っているの」
「おいおい? ぼくらのちいさな提督はなんでそこまで知っているんだ? この子のまえで照明弾なんて使ったことないぞ?」
「まえに『キュアレス』探検の記録を見せたのよ。わたしたちがあの惑星で海溝のなかを照らしたときの映像」
「ああ、なるほど。あれは綺麗だったからなあ」
「この子の知っている世界といえばそんな映像だけなのよね。考えれば可哀想――そうね、ミヒョンの提案をいれて試しに何発か撃ってみましょうか? 照明弾」
「うーん、大丈夫かな? 敵対行為ととられない? 『ハルバン』のときみたいに怒った『蜘蛛』に襲われたくはないからな」
「穴の中心線を狙えば『辺(エッジ)』にはかすり傷ひとつつきゃしないわ。すくなくとも内部のかなり奥まで見通すことができるでしょう。『蜘蛛』なら心配ないわよ。いくらなんでもここまで飛びついてはこられないはず」
*
カシルは船を巧みに操り傾いた『辺(エッジ)』の中心線にもっていくと慎重にランチャーの狙いをすませた。
「いい? 撃つわよ――3、2、1、発射!」
ひゅん!というこごもった発射音を残して照明弾が撃ちだされた。それは狙い通りまっすぐな軌跡を描いて『辺(エッジ)』内部の空洞を飛翔していき、数秒のち暗がりのなかで閃光が炸裂した。
手を叩いてはしゃぐミヒョンと歓声をあげるユルグをしり目にふたりは倍率最大のモニター画面を凝視した。
「完全にからっぽだわ。少なくとも数キロ奥まで同じ調子――これはやっぱりただの大きな紙筒ね」
「どうだろう? 『蜘蛛』たちが内部の構造材をすでにかたづけてしまった後だとしたら……?」
「うーん、ふつう順序が逆でしょ? 仮にこの『チューブ』が雨風よけのカバーだとして、内部にしっかりした構造があったなら、解体業者はまず外壁を取り去ってからおもむろに骨組みのほうにとりかかると思わない?」
そうだな、とつぶやき何気なく観測窓の外に目をやったとたんウィリアムの心臓は凍りついた。子供たちがすがりついている透明樹脂の外、ほんの十数メートルの位置にいつのまにか見たことのない形状の巨大な機械が浮かんでいたからだ。
「ユルグ! ミヒョンを連れて今すぐ窓から離れなさい!」
ウィリアムが反応するより早くカシルの緊張した声がとんだ。いっしゅん空白になっていた彼の心もすばやく回転をはじめ慎重な口調でウィリアムは妻に警告した。
「真北の方角にべつの一機。南にもちょっと離れてさらに一機。あわせて三機いる。あわてて動かないほうがいい。相手のボディをよく見てみるんだ」
「見えるわ。でっかい推進装置がついている……これって、やっぱり『蜘蛛』の仲間かしら?」
「新種だな。どうも見たところエアインテークつきのジェットエンジンに思えるんだ。しかもかなり強力なやつがふたつ。気にいらないな。全体のデザインも空力を考えた大気圏内飛行用――こいつらよほど素早いぞ。本気で攻撃されたらちょっと防ぎきれそうもない。刺激しちゃだめだ」
「このままの姿勢でゆっくりと後退するわ……やっぱり照明弾はまずかったかな」
「後悔してもあとの祭りってやつだ。まあ『辺(エッジ)』に実害を与えたわけじゃないし、何ごともなく見のがしてくれるといいんだが……」
まるでスズメバチの巣にうっかり出くわしてしまったハイカーといった有り様で『サガ』は足音をひそませるようにしてお尻から退いた。相手も距離をたもったままついてくる。空気抵抗分を補うべく制御噴射音が短く響くたびウィリアムは冷や汗が背中を流れるのがわかった。
「どうも『辺(エッジ)』を架け替えるとき、はじめにケーブルをどうやって渡すのか気にはなっていたんだよ。やっぱり空を飛べる作業ユニットがいたんだ。たぶんこいつらのほかにもいろいろなタイプがあるんだろうな」
「例によって後知恵だわね。ちょっと考えればわかりそうなことなのに気づかないもんだわ……背後にかなり大きな雲がある。あのなかにまぎれこみましょうか」
「うん、どうやらこいつら今のところ攻撃する意図はないようだけど、こうぴったりまとわりつかれていてはうっとうしくてかなわない。うまく逃げ切れるかな?」
茜雲浮かぶのどかな空間での息詰まる時間だった。たぶんこの機械たちはカメラとレーダーでこちらを認識しているはずだ。それなら雨雲に隠れて姿をくらませることは可能だろう。
「気流が不安定になってきた。ここは折れた『辺(エッジ)』が作る乱流が重なりあう場所なんだろうな。ユルグ、ミヒョン、加速シートに座ってシートベルトをしていなさい」
『ジェットスパイダー』たちとの距離がすこしひらいたようだ。観測窓に細かい水滴が付着しはじめてその姿がにじんでいる。たぶん相手からもこちらがはっきりと視認できなくなっているはずなのだが――。
「モニターカメラのドームにも雨粒がついてきている。この世界を飛ぶときにはワイパーが必要不可欠ね」
「……またまた後知恵ですまないけど、いま思いついた。たぶん奴らのカメラはワイパーつきだぜ」
「ひゃっ……そうか!」
「この際、完全に雲のなかに隠れるしかないよ」
「最悪だわ。ほとんど見通しがきかない状態で水滴だの岩石だのがぷかぷか浮かぶ空間のしかも乱気流のなかにつっこむっていうんだから……モニターを赤外線モードに切り替えて手探りで飛ぶしかないわね」
カシルは一瞬バーニアを全力噴射させ、『サガ』はミルクのように白濁した空間に突入した。
「うまくいきますように! ――これで連中を撒けなきゃ生涯まとわりつかれたままだぞ」
ふたりは『ジェットスパイダー』たちがあきらめて去っていってくれるまで隠れているつもりだったが、いざ試してみるとどうやらあまり長く雲の中にはいられないらしいことがわかった。『サガ』の球形の船体は空気抵抗も大きく乱流のなかの飛行はまるで快適とは言えないのだ。加えて雨粒がレーダーを混乱させ、赤外モニターの画像もせいぜい数百メートル先をぼやっと浮かび上がらせるだけだから、カシルの感じているストレスはウィリアムにも容易に想像がついた。ちょうど昔の船乗りが夜の嵐をついて帆船を走らせているようなものだろう。『暗礁』ならぬ浮遊する岩石にぶちあたる危険もかなり高いはずだ――。
「ママー、ミーちゃんが気持ちわるいって」
ユルグの声にウィリアムははっと我にかえった。
「――ミヒョン。こんなところでもどさないでくれよ。いい子だからもうすこしだけがまんしなさい――やはりこれは無理だな。早めに雲から出たほうがいい」
「そうね。切れ目をさがします」
青い顔で健気に耐えているミヒョンを抱きかかえるようにしてウィリアムは無重力バスルームへ連れて行った。遠心力が加わると機体の揺れはむしろいっそう強く感じられるようになった。ぐったりしている妹を心配そうに見つめるユルグの顔色も決してよくはない。つい弱音めいた言葉がウィリアムの口からでた。
「……おとうさんはちょっと後悔しているよ。こんな危険があるとわかっていたらおまえたちを連れてきはしなかった。これをうまく乗り越えたら早いうちに『ラブソング』に帰ろうと思う」
しかしミヒョンの背なかをさする父親を上目づかいで見上げながらユルグは激しく首をふった。驚いたことにはミヒョンまで力なげながらも首をふっている。
「なんだい、ミーちゃんまで? 帰るのは嫌か?」
兄と妹は申し合わせたようにかくんかくんとうなずいた。
「ふうむ、これぐらいの目にあったぐらいで逃げ出すつもりはないってわけか?」
――かくん。かくん。
やれやれ、ほんの少し前まではか細い泣き声をあげるだけのちっぽけな物体だったくせに、いつのまに……ウィリアムは熱いものがこみあげてきた喉元を咳払いでごまかし子供たちににっと笑いかけるといった。
「そうだな、わかった……そうとも、目のまえで新世界がいままさに踏破されるのを待っているんだ。セイジ一家はこんなことで音をあげたりするものか」
彼はふたりの小さな肩に自分の手をしっかりと置いてバスルームの回転が止まるのを待った。
「……パパ、『踏破』って?」
「うん? つまりがっちり踏むことさ」
「無重力なのにどうやって『踏む』の?」
*
父親と子供たちが制御ルームに戻ってくるのと観測窓の外が明るくなるのとが一緒だった。そこはふたつの雲の山脈に挟まれたような場所で頭上にはジオデシックの編目越しに薄暗くなった紺碧の空と幾つか星も見えた。
「だいじょうぶ?」
「ああ、子供たちなら元気だよ」
「よかった。こちらもどうやら逃げ切れたみたいよ。周囲にそれらしい影はないわ」
ウィリアムは安堵のため息をついた。
「あるいはいまのが一番懸念していた事態だったかも知れないな。まあ、無事にすんでよかったよ。たぶんもうあの場所にもどることもないだろう」
「いつのまにやらちょっと明るくなっているわね」
「うん……雲のなかにいる間に日付がかわってしまったんだ。はや夜半をすぎて早朝だよ。探検開始二日目だな」
真夜中でも完全に暗くなることのないこの世界では黄昏から朝焼けへと一足飛びに変わってしまうかのようだった。夜のない世界――なんだか損をしたような気分だ、とウィリアムは思った。
「いまの雲の中での操船で姿勢制御用の推進剤をずいぶん使っちゃったわ。補給しなくては」
「見てご覧――あそこにいくつか水球が溜っている場所があるだろ。あそこへ行って水をわけてもらおう」
「わけてもらおう、か――まるで旅の途中で立ち寄る谷間の村じゃないの」
「なんだかひと波乱乗り越えてすっかりこの世界の住人になった気分だよ」
目的地に到着するまえにふたたび雲にまとわりつかれることを心配したが、むしろあたりは急速に晴れわたりつつあった。気がつかないうちに大気の循環が『サガ』を乱流の外へと運んでいたのだ。ふりかえると例の『イレギュラー』もかなり遠くに離れている。
「どうやら自転の影響がこのあたりの大気にまで及んでいるようね」
「うん。たぶんいま船を運んでいるのは自転にともなう遠心力で外殻へと運ばれ内側から赤道部分にぶちあたった西むきの気流が、南北両半球に向かうときにコリオリの力で東むきに偏向した――その風のはずだな」
「地球で言うところの偏西風?」
「そういうことになるね。ここでは緯度による寒暖の差がほとんどなく亜熱帯の高気圧帯も存在しない。だから地球の貿易風にあたるものもなく、部分的な乱流はあっても球殻全体で西から東へ向かう基本的な大気の流れがさまたげられることがない。その意味でこの世界は地球より木星に近いと言えるかもしれない……」
「だから台風が発生することはないはず――でも以前それらしい雲をちらりと見たことがあるわね」
「なにか別のメカニズムがあるんだろうな。木星に大赤班があるように――おいおいそれらも理解できるようになると思うよ」
「それまで何年かかるかわからないけど……」
ウィリアムがそれに答えようとしたとき、とつぜん『サガ』の船体になにか無数の小さなものが雨あられとぶつかる音が聞こえた。
「こんどはなんだ? この音は?」
「ほら! 見て!」
カシルが観測窓を指さして叫んだ。ウィリアムはいっしゅん何が起こっているのかわからなかった。窓の表面に無数の黒い斑点が現れみるみるその数を増しつつあった。
「黒い雪? 炭化物の浮いている空域につっこんだかな?」
「そうじゃないわ! これ生きている! 『サガ』が襲われているのよ!」
ウィリアムはぞっとした。斑点だと思ったのは羽をひろげると掌ほどあるゴキブリに似た生き物だった。数かぎりないそれらがぺったりと船体にとりついてきているのだ――彼の脳裏に脈絡のないまま、ふとずっと以前に見た蜜蜂を身体中にとまらせた地球の養蜂家のイメージが浮かんだ。
「でもどうして? 何かこいつらを刺激するようなことをしたのかな?」
「まずいな。観測窓だけじゃなくカメラのドームにもおしよせてきている。外が見えなくなるわ!」
すべてのモニター画面がうじゃうじゃ動く黒い虫たちで埋め尽くされそうになっていた。
「レーダーにきりかえるんだ。早くしないと衝突する。そこら中に岩だの水玉だのがごろごろ浮いているぞ……」
「うーん、だめ。レーダー波も妨害されている……」
「ちくしょう、この虫の群れが撹乱してるんだ。波長を変えて――」
そう言い終わる前にカシルが何かを叫び、ついでショックとともに轟音が船体を打ち鳴らした。はずみで投げ飛ばされ内壁の内張にいやというほど叩きつけられて彼はいっしゅん息がとまった。 つづく |