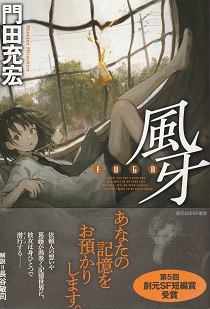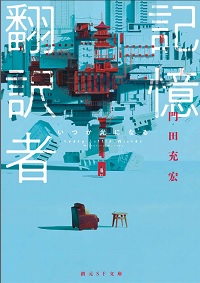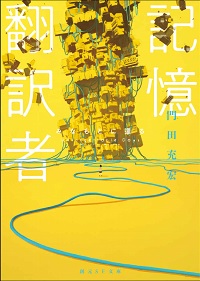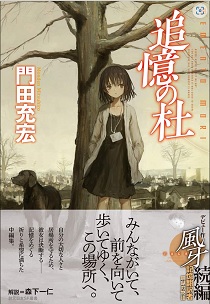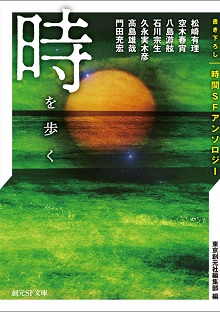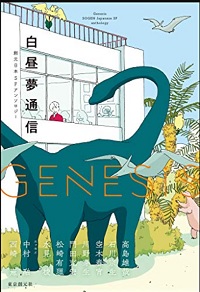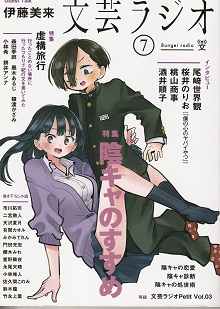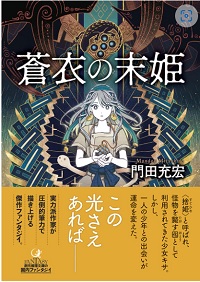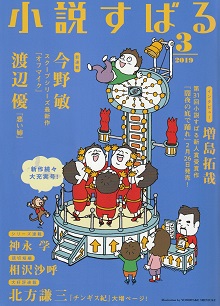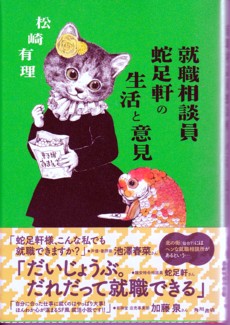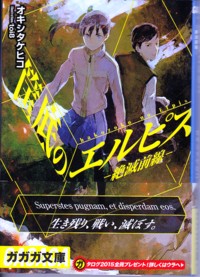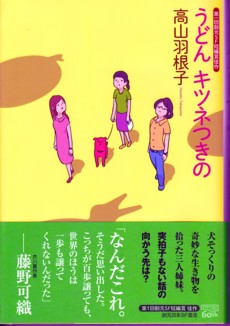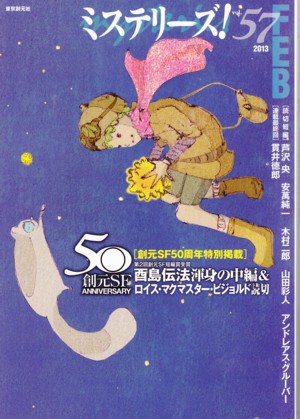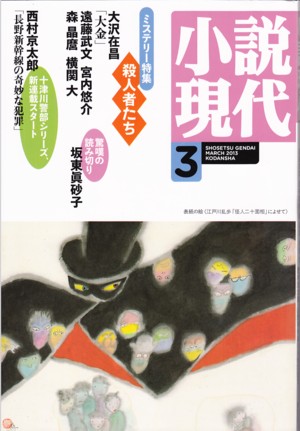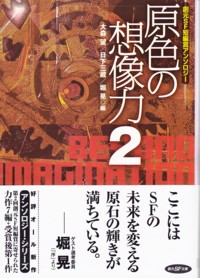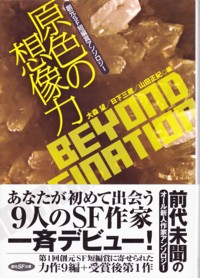《記憶翻訳者》シリーズの粗筋は、最初から順番に読んで頂くと分かりやすいと思います。
粗筋は、ネタバレも考慮して、門田充宏先生の「公式サイト」の「WORKS」から大幅に引用してます。雑誌掲載短編、Web掲載短編の粗筋も、公式サイトの「WORKS」にあります。
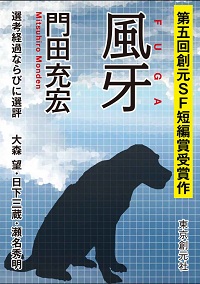 「風牙」門田充宏著
「風牙」門田充宏著
2014.8.8、東京創元社、Kindle版、220円
第5回創元SF短編賞受賞作
主人公の珊瑚は過剰共感能力者で、彼らは他人の感情に共感しすぎてしまう特異な体質のために、社会生活に支障をきたしてしまっている。珊瑚は、他人の感情と自分の感情を区別できないレベルの能力者故に、過剰共感能力を抑制するインプラントの助けを借りるまで、自我を発達させることが出来なかった過去を持っていた。生きづらさを抱える彼らの共感能力を生かし、本来はその持ち主にしか理解できない記憶を第三者にも分かるようにする“記憶翻訳”の技術を開発したのが九龍という企業だった。珊瑚はその中でもトップクラスの実力を持つ記憶翻訳者に育った。
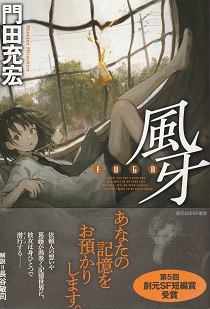
『風牙』門田充宏著、しおんカバーイラスト
2018.10.31、創元日本SF叢書、2200円、Kindle版1935円
収録作:「風牙」「閉鎖回廊」「みなもとに還る」「虚ろの座」
この『風牙』は、以下の二冊に、改題・分冊・増補されて文庫版になっています。
『記憶翻訳者 いつか光になる』は、「風牙」「閉鎖回廊」+「いつか光になる」「嵐の夜に」
『記憶翻訳者 みなもとに還る』は、「みなもとに還る」「虚ろの座」+「流水に刻む」「秋晴れの日に」
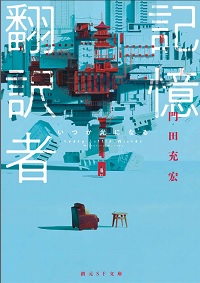
『記憶翻訳者 いつか光になる』門田充宏著、日田慶治装画
2020.10.23、創元SF文庫、Kindle版、920円
「風牙」
インタープリタとは、個人個人によって独自のものである人の心から抽出した記憶データを“翻訳”し、他者に理解可能なよう立体的に再構築する技能者である。業界トップレベルの女性インタープリタである珊瑚が受けた仕事は前例のないものだった。”潜行”する先は、彼女自身の会社の社長の記憶。しかし珊瑚に先立って送り込まれたインタープリタ3人が、何れも社長の記憶の中で正体不明の存在に襲撃され病院送りとなっていた。社長の記憶世界でいったい何が起こったというのか。珊瑚は”統合サポートシステム”の孫子と共に、社長の記憶世界にアクセスする……
「閉鎖回廊」
珊瑚のもとに、かつて共にインタープリタの導入研修を受け、今はトップクリエイタとなっている由鶴から奇妙なメッセージが届く。「お願い、今すぐ〈閉鎖回廊〉を止めて」。自分が作成した、疑験都市〈九龍〉で最大の人気を誇るコンテンツ、〈閉鎖回廊〉を由鶴は何故止めろと言ってきたのか? 連絡が取れない由鶴の事務所を訪れた珊瑚は、主のいない開発室で、由鶴の過去を巡る九つの記憶が保存されたモジュールを発見する。
「いつか光になる」
九龍の新しい事業、プロモーション用記憶翻訳。その提案者でもあり、記憶データ提供者でもあるハルには人生を賭けた密かな目的があった。ハルと共に新規事業に取り組む珊瑚は、その過程でハルと人生の一部を共有していく。ハルが目指していたものは、そしてその結末は……
「嵐の夜に」
台風で電車が止まってしまった夜、珊瑚はハルと共にオフィスに泊まることになってしまった。嵐の中、少しだけぎくしゃくしていた二人に訪れる、静かで暖かな時間が……
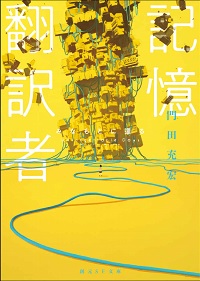 『記憶翻訳者 みなもとに還る』門田充宏著、日田慶治装画
『記憶翻訳者 みなもとに還る』門田充宏著、日田慶治装画
2021.2.12、創元SF文庫、Kindle版、950円
「流水に刻む」
疑験都市〈九龍〉の第二階層、二狐。ファンタジイ世界を再現したこの階層に、本来登場しないはずの人間ー少年のNPCが出没する。少年は九龍側の制御を受け付けず、自由に二狐内を行動していた。珊瑚はプレイヤーのひとりとして光の妖精となり、同じくミノタウロスとなった上司の眞角と共に、少年を捕らえるために全力で鬼ごっこを繰り広げることに。果たして少年の正体、そしてその目的は。
「みなもとに還る」
レビューを依頼された疑験都市コンテンツの中で、珊瑚はうなじからどこまでも長く伸びる〈結びの緒〉を生やした子供、マヒロに導かれ、母と名乗る存在と出会う。もういないと聞かされていた母の存在に動揺した珊瑚は、導かれるように〈仮集殿〉と呼ばれる場所へと赴く。そこは、過剰共感能力者たちが肩を寄せ合って暮らす、〈みなもと〉という名の組織の本拠だった……
「虚ろの座」
探偵の調査結果に従い、私は共感能力を礼賛する新興宗教団体、〈みなもと〉へと入信する。それがただひとつ、失った妻と子へと繋がる道だと信じて。だがそこで私を待っていたのは、考えてもいなかった出来事だった。
「秋晴れの日に」
珊瑚は二ヶ月ぶりに〈みなもと〉の仮集殿を訪れ、都や真尋と再会する。珊瑚には密かに心に決めた、小さな目的があった。
(著者談:こちらは「みなもとに還る」の後日談であり、珊瑚の決心の物語でもあります。)
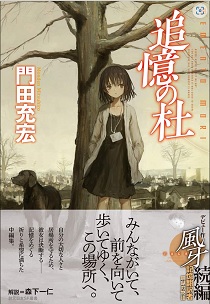 『追憶の社』門田充宏著
『追憶の社』門田充宏著
2019.5.11、創元日本SF叢書、2585円、Kindle版1834円
収録作品:
「六花の標」
珊瑚が翻訳した記憶データが、ネット上に無制限に公開され始める。急死した料理研究家・雪肌女の最後の日々と、彼女と一緒に暮らしていた少年・仁紀の記憶――それが雪肌女の遺志だからと、仁紀は自分にとって大切な日々の記憶を公開し続ける。その結果、他人の記憶を覗き見ることを楽しむ人間が多く出る一方、記憶データの翻訳自体や、サービス提供元である企業・九龍に対する批判までが起こるようになってしまう。珊瑚は九龍と仁紀を護るため、雪肌女の本当の意図を探ろうするが……
「銀糸の先」
記憶データのレコーディングを実施中のユーザが殺害され、記憶データが持ち去られるという事件が連続して発生する。記憶データはレコーディングされただけの状態では他者は理解できないため、翻訳のためにそのデータは九龍に持ち込まれたのではないかとの推測が流布するが、捜査中であるため九龍はノーコメントを貫いている。そのことが疑念を呼び、また仁紀の事件のあとであったこともあり、九龍に対しての批判が巻き起こる。その対応のため、九龍は自社の仕事を理解して貰うため、若手ジャーナリスト・香月に珊瑚へのインタビュー実施を許可する。あわよくば殺人事件の手がかりを入手しようと考えていた香月だったが、インタビューセッションは彼の予期しない方向に動き出す。
「追憶の杜」
統合サポートシステム<孫子>が作り出した疑験コンテンツのレビュー中、珊瑚は存在するはずのない動的要素を見てしまう。孫子にも、モニタしているエンジニアにも上司にも見えないその存在は、まるで珊瑚を導くかのように姿を見せつつ進んでいく。珊瑚が辿り着いた先には、あり得ないはずの空間と、あり得ないはずの経験が待っていた。
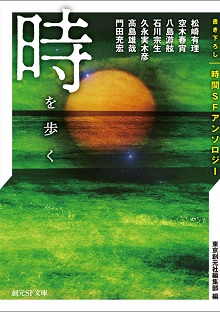
『時を歩く 書き下ろし時間SFアンソロジー』東京創元社編集部編、瀬戸羽方装画
2019.10.31、株式会社東京創元社、Kindle 版、855円
収録作:
「未来への脱獄」松崎有理
「終景累ヶ辻」空木春宵
「時は矢のように」八島游舷
「ABC巡礼」石川宗生
「ぴぴぴ・ぴっぴぴ」久永実木彦
「ゴーストキャンディカテゴリー」高島雄哉
「Too Short Notice」門田充宏
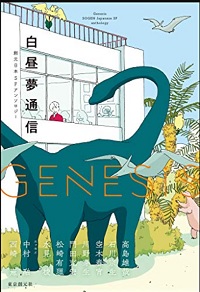
『Genesis 白昼夢通信』創元日本SFアンソロジー Kindle版、2019.12.20、1980円
【収録作】
高島雄哉「配信世界のイデアたち」
石川宗生「モンステリウム」
空木春宵「地獄を縫い取る」
中村融〔エッセイ〕「アンソロジーの極意」
川野芽生「白昼夢通信」
門田充宏「コーラルとロータス」
西崎憲〔エッセイ〕「アンソロジストの個人的事情」
松崎有理「痩せたくないひとは読まないでください。」
水見稜「調律師」
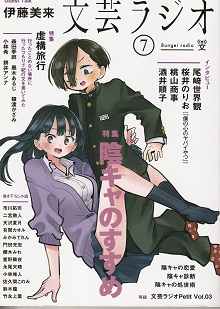 「文芸ラジオ7号」、2021.6.1、メタブレーン、1100円
「文芸ラジオ7号」、2021.6.1、メタブレーン、1100円
〇Guest Talk 伊藤美来「あまり飾らないで、背伸びをしすぎず、自然体で表現する」
〇特集 陰キャのすすめ
〇特集 虚構旅行 行ったことのない場所に行ったつもりで紀行文を書いてみた
〇小説・散文 門田充宏「社会的舞踏(ソシアル・ダンス)」櫻木みわ「セヴンデイズ」
〇Book in Book 再録 文芸ラジオPetit Vol.03
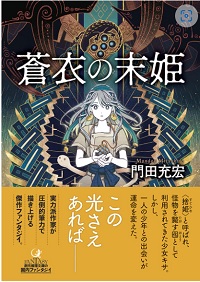
『蒼衣の末姫』門田充宏著、シライシユウコ
2021.9.24、創元推理文庫、968円、Kindle版855円
地を這い空を飛び、甲殻で身を固め無数の脚で爪でひとを屠る巨大な怪物、冥?(みょうふ)が跋扈する世界。翻弄されるだけだった人類は壁を築き堀を巡らせた城塞都市〈宮〉を造り、宮ごとに防衛、工業、商業などと機能を特化することで冥?の脅威に抗っていた。
十六歳の少女キサは、ひとを圧倒する冥?を滅ぼすことができる能力を有する蒼衣(そうい)の血を引きながら、僅かな力しか持たないため、冥?を集めるためだけに、囮として最前線に連れ出されていた。だがある日、冥?の前例のない攻勢によって作戦は失敗に終わり、キサは人類と冥?に有毒である水の流れる川へと落下してしまう。
そのキサを救ったのは、生(いくる)という十五歳の少年だった。棄錆(きせい)として大人たちから切り捨てられた生も、命を危険に晒す仕事を毎日続け、懸命に生きてきた存在だった。
自分の命を捨ててでも、ひとという種を繋ぐことを考えねばならない世界で、囮の姫と見棄てられた少年は手を取りあい、蔑まれてきた力と心とを振り絞って、襲い来る脅威、そして課せられた運命に立ち向かう。

『2084年のSF』日本SF作家クラブ編
2022.5.25、ハヤカワ文庫JA、Kindle版、1188円
収録作品:池澤春菜「まえがき」
【仮想】福田和代「タイスケヒトリソラノナカ」、青木和「Alisa」、三方行成「自分の墓で泣いてください」
【社会】逢坂冬馬「目覚めよ、眠れ」、久永実木彦「男性撤廃」、空木春宵「R__ R__」
【認知】門田充宏「情動の棺」、麦原遼「カーテン」、竹田人造「見守りカメラ is watching you」、安野貴博「フリーフォール」
【環境】櫻木みわ「春、マザーレイクで」、揚羽はな「The Plastic World」、池澤春菜「祖母の揺籠」
【記憶】粕谷知世「黄金のさくらんぼ」、十三不塔「至聖所」、坂永雄一「移動遊園地の幽霊たち」、斜線堂有紀「BTTF葬送」
【宇宙】高野史緒「未来への言葉」、吉田親司「上弦の中獄」、人間六度「星の恋バナ」
【火星】草野原々「かえるのからだのかたち」、春暮康一「混沌を掻き回す」、倉田タカシ「火星のザッカーバーグ」
榎木洋子「SF大賞の夜」
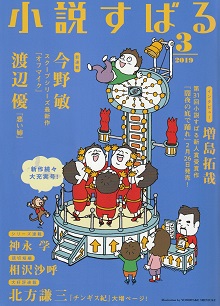 『小説すばる』2019年3月号
『小説すばる』2019年3月号
●私的偉人伝「心のノート」門田充宏作
●清水建設×日本SF作家クラブ【建設的な未来】
第2話「理想の小説家」門田充宏作
第18話「恋する海中都市」門田充宏作
●SF Prologue wave
「ミーティエイター」門田充宏作
●日本SF作家クラブ
『楽日』(前編)門田充宏作
●シミルボン
門田充宏先生インタビュー「そもそもSFはあまり読んでいなかった」
●Web東京創元社マガジン
門田充宏『蒼衣の末姫』(創元推理文庫)ここだけのあとがき
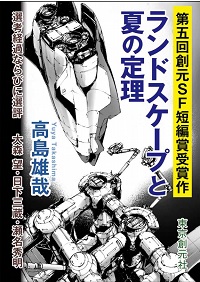 「ランドスケープと夏の定理」第5回創元SF短編賞受賞作(門田充宏「風牙」と同時受賞)
「ランドスケープと夏の定理」第5回創元SF短編賞受賞作(門田充宏「風牙」と同時受賞)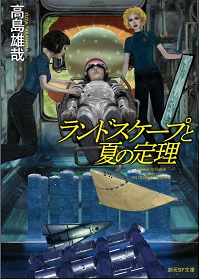
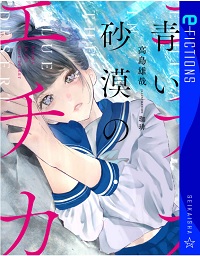
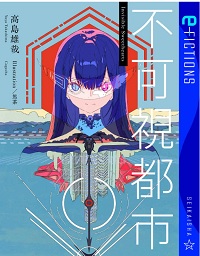

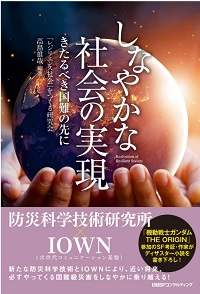
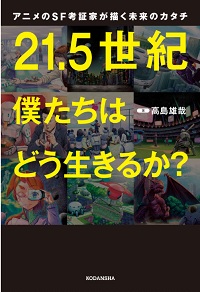 《機動戦士ガンダム 水星の魔女》
《機動戦士ガンダム 水星の魔女》
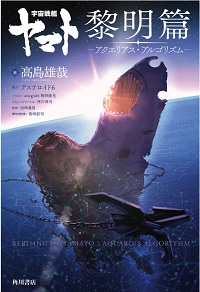
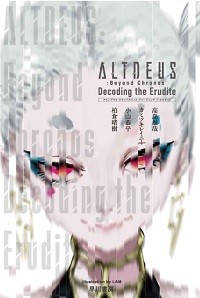
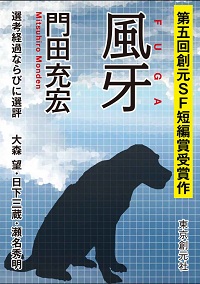 「風牙」門田充宏著
「風牙」門田充宏著