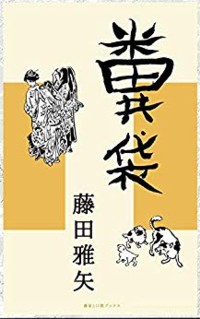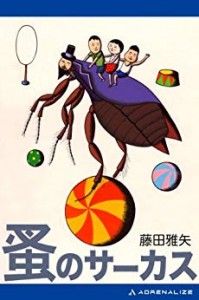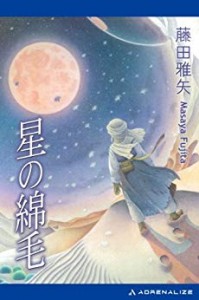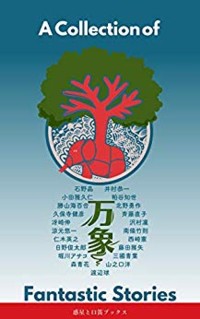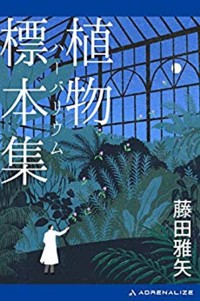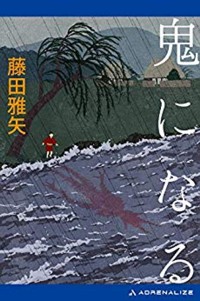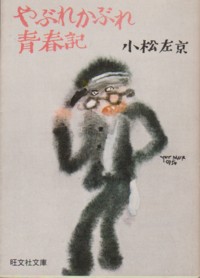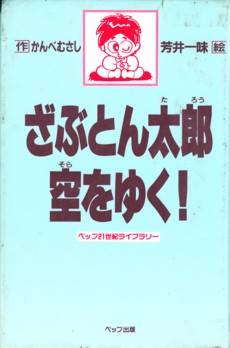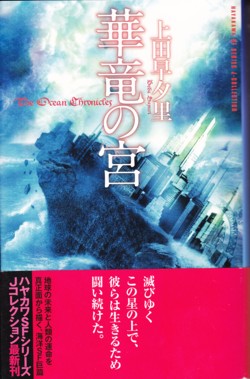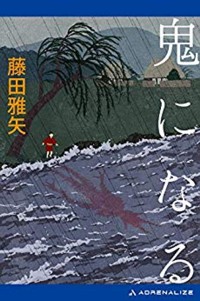
『鬼になる』<怪奇篇>藤田雅矢著、ウエタケヨーコ装画
2018.8.21、株式会社アドレナライズ、Kindle版、495円
初出《異形コレクション》、SFマガジン他から
収録作:
「鬼になる」
天保四年、水口村。度重なる飢饉で村民は疲弊していた。医者である宇根次さまの屋敷には異人が出入りし、飢えた子どもを預ければ“一年間”は食べさせてもらえるという噂があった。最後の一行がグサリときます。
「暖かなテント」
サーカスを見に来たマサルは、そこで不思議な体験をする。象やライオンがいるとは思えない、一見するとみすぼらしいそのサーカス団にはある秘密があった。
「引きだし刑」
ダリの《引き出しのあるミロのビーナス》に感化された作品。
「引きだし刑」に処された男が送り込まれる『引きだし等により構築された迷路世界』。そこから帰還したものはまだ居ないが、コードネーム<シーラカンス>という貴重なものを探し出せれば解放されるという。そこは暗黒の世界で、男は辺りを照らす小さな<太陽>とロッカーのカギを渡された。
「幻肢(ファントム)の左手」
火葬場の責任者である俺の左手が疼く。俺は、かつて同級生だった淳と美紀子の三人でよく山登りに行ったものだった。しかし大学時代に登った冬山で雪崩に襲われ、淳は助かったものの左手と左足を失ってしまった。そして美紀子はなんと一年半後に白骨死体となって見つかったのだが……
「釘拾い」
藤田さんの生まれ育った京の町のはなし。
石像寺の釘抜地蔵、釘ではない「釘」を踏んだマーちゃんは、祖母に連れられて百恵ばあちゃんに「釘」を抜いて貰いに行った。その「釘」が見える人は歳をとったら「釘拾い」をすることになるという。
「舞花」
英国のキュー植物園には、高名なノース女史が描いた植物画があり、その中には存在を確認されてない浮遊する植物が描かれていた。植物園が契約している世界を駆けめぐるブラント・ハンターが、その「舞花」を持ち帰ったというが……
「Dovey Junction」
ウェールズ地方を旅行した際に乗り換えた名も無き駅での不可思議な話。
「最後の象」
最新型のドローンを使って像を狩る密猟者。それを暗視ゴーグルで見つめる男の正体と象の秘密とは……
「おちゃめ」
「おちゃめ」を見た日には、ちょっといいことがある……
「銀のあしの象」
象専用パワードスーツをつけた動物園のシルバーは、何か悪いことが起こりそうだと嫌な匂いを感じるのだった。
小学5年生向けた作品。
「歯神社」
第二回大阪てのひら怪談投稿作品。
「鉄塔の記憶」
鉄塔のある風景を詠んだ句集。
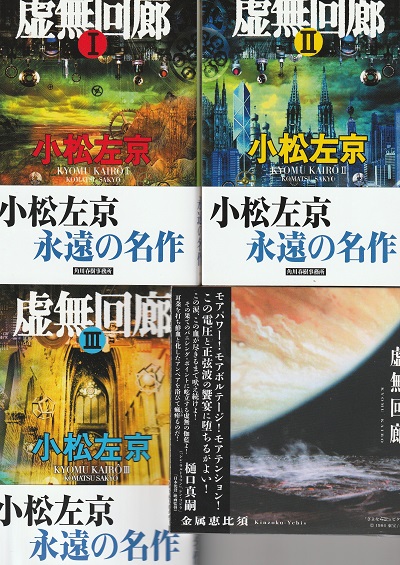 『虚無回廊』三冊とCD『虚無回廊』
『虚無回廊』三冊とCD『虚無回廊』 CD裏面に乙部順子さん(元・小松左京マネージャー)の紹介文あり
CD裏面に乙部順子さん(元・小松左京マネージャー)の紹介文あり